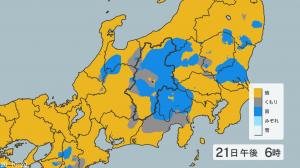「伊勢講」を行った長野市長沼地区六地蔵町の有志
特集は災害を乗り越えた伝統行事です。2019年の台風19号で被災した長野市長沼地区の六地蔵町の有志が、代表者を選んで伊勢神宮を参拝する「伊勢講」を9年ぶりに行いました。地域の復興と共に前に進もうという住民の思いで復活させました。
■住民が9年ぶりに「伊勢講代参」

六地蔵町伊勢講 代参人・落合道雄さん(中央)
「伊勢に行きたい 伊勢路が見たい せめて一生に一度でも」
江戸時代からこう歌われてきた伊勢神宮。「伊勢参り」は昔から人々の憧れでした。
2月28日、その伊勢の地を訪れたのは長野市長沼地区「六地蔵町」の住民たち。地域の代表者が参拝する「伊勢講代参」と呼ばれる伝統行事です。
台風19号災害や新型コロナの影響で中断していましたが、2025年、9年ぶりに復活させました。
六地蔵町伊勢講 代参人・落合道雄さん(84):
「新鮮な気持ちでございます。何年ぶりかで来てみたんですけど、これからもずっと続けていければいいなと」
■江戸時代以降、全国に広まる

講帳
明治27(1894)年から130年余り続く六地蔵町の「伊勢講」。代々引き継がれてきた記録文書「講帳」には。
(講帳)
「信仰者の話し合いを以て、毎年代参の者を定め伊勢神宮に参拝するものとす」

昭和の伊勢講(提供:旧長沼公民館)
金銭的にも日程的にも負担が大きかった伊勢参り。江戸時代以降、農家の有志が「講」をつくって費用を出し合い、地域の代表「代参人」が五穀豊穣や安全を願う「伊勢講」が全国的に広まりました。
代参人が無事に戻ると、付き添ってきた神様を伊勢に戻す「下降式」という儀式を行います。
一連の儀式は、県内でも盛んに行われてきましたが、昭和の高度経済成長の中でその意義が薄れていき、行う地域は少なくなっていきました。
■行う地域が減っても継続 理由は

2010年代の「六地蔵町伊勢講 下降式」(撮影:田中愛子さん)
しかしー
2010年代、六地蔵町が行った「伊勢講」。加わる住民は減りましたが、それでもほぼ毎年続けてきました。
県内の伝統行事や風習に詳しい郷土史家の宮下健司さんによりますと、県内で下降式まで行うのは六地蔵町が唯一とみられるそうです。