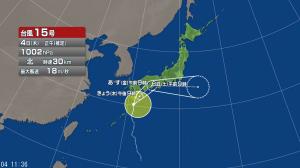体感温度は40℃に
その感覚を必死で覚える大木島さん。夏場の作業場の体感温度は40℃に。
大木島蓮さん:
「夏にやるようなもんじゃないので、そこが苦しいところ」
石田さん:
「かなりきついからね、この仕事。とにかくあきらめないで頑張って、維持していく、気持ちも維持していかなきゃならないし。同じことだってあきれるほどやってもらいたい」

「泥落とし」
鎌が冷めたら次の工程は「泥落とし」です。
石田さん:
「もう少し刃を立てるんだよ、鋼の方、そうそれでいい」
大木島蓮さん:
「(何してる?)これは焼きが入っているか、入っていないかを(鎌をこすって)確認する作業。焼きが入っていないと、音がちょっと鈍いような、滑るような音なんですけど、これが焼きを入れると、ちょっと高い音が鳴る」
確かに焼き入れ後は音が高いことが分かります。
石田さん:
「(大木島さんの焼き入れは)うまくいっているよ。これさえ正確に入っていれば、あとは刃を研げば必ずよく切れるはずだ」
大木島さんは、これで鎌づくりの工程を一通り学びました。
大木島蓮さん:
「まだまだここからじゃないかと。今はもっと練習しないと」

木田弁治商店の8代目・木田尚也さんに見てもらう
この日、修業が終わってから向かったのは打刃物を扱う老舗「問屋」です。
大木島蓮さん:
「石田さんから6本いいって言われたので、見ていただいて」
木田弁治商店・木田尚也さん:
「石田さんが確認してくれたってことだね」
明治時代後期から続く老舗の8代目・木田尚也さんに自分で作った鎌を「商品」として見てもらいます。鎌の確認は単なる「検品」ではなく「信州打刃物」としての品質と信頼を守るための最終審判。厳しいチェックが入ります。
木田さん:
「ちょっとこれコミ(鎌の刃と柄をつなぐ部分)が太いので、普通このくらいの柄を付けると細くないと。全体的にちょっと太いよね」