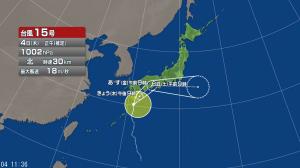「鍛造」
60年ぶりの「新弟子」大木島さん。
石田さんのもと、これまで、鋼を叩いて形を作る「鍛造」や鎌の形にした鋼を削り刃を付ける「研ぎ」などを訓練してきました。

「研ぎ」の出張サービス(2025年3月)
2025年3月には千葉県のイベントで「研ぎ」の出張サービスも経験。
石田さん:
「試してみてください。だめだったら研ぎ直します」
「研ぎ」を依頼した客:
「スパスパ!」
大木島蓮さん:
「(初めてお金もらっての仕事で)責任を感じる仕事でもあるので、喜んでもらえたときの達成感はその分ある」

「焼刃土」を塗る
修業を始めて1年4カ月。次のステップに進みます。
「焼入れ」です。ガス炉で800℃近くまで熱した鋼を水に入れ急激に冷やすことで組織を硬く、粘り強くする作業です。「刃物に命を吹き込む」重要な工程です。
まず、炉に入れる前の鎌に粘土質の泥「焼刃土」を塗っていきます。
石田さん:
「効能は(泥を塗らずに急激に冷やすと)水と鎌の間に水蒸気の膜ができる。(泥を)塗ってあると一気に(水を)吸い込む、0.何秒でキューっと吸い込む、すると、急に冷えるからあまり(鎌が)曲がらない」

熱せられた鋼を水で冷やす
その後、1300℃に熱せられた炉の中へ。
全体が赤くなったら水で冷やします。
大木島蓮さん:
「全体的に赤くなるかというところと、水に入れるタイミング。入れた後、何秒入れなきゃいけないかを意識しています」

ガス炉で800℃近くまで鋼を熱する
熱しすぎると「もろく」なり、足りないと「柔らかく」なる鋼。さらに水で冷やす時間が長すぎると「焼き割れ」などを起こし、短すぎると柔らかくなってしまう繊細で重要な作業です。
その見極めに「職人の技」が出ます。
石田さん:
「品物によっては厚いのと薄いので冷える時間が多少違うので、(水に入れたときに)握っているとここ(手)が電気が来たようによくわかる、びりびりって。周りで見てたらわからない、音しか聞こえないでしょ。それはほとんど勘、目をつむっていたって(わかる)」