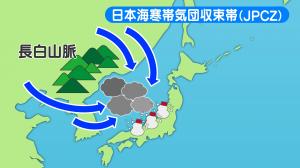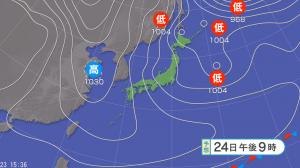■京都・西本願寺の国宝「御影堂」も

18万枚のこけら板を作った善光寺の山門
屋根に葺く「こけら板」。
芝居などの初公演を「こけら落し」と呼ぶのは、屋根に残った板を落として初日を迎えたことに由来します。

善光寺山門の「平成の大修理」(2002年~2007年)
栗山木工は多くの国宝や重要文化財の「こけら板」を手掛けてきました。善光寺山門の「平成の大修理」。この時も栗山木工のこけら板で屋根が葺き替えられました。作った板は18万枚。1年余りは休日返上だったそうです。
国の重要文化財・上田市の前山寺 三重塔のこけら板も。
映っているのは栗山さんの弟・光博さん。実は兄弟3人とも職人となり、会社を盛り立ててきました。
栗山さんが一番の思い出と語るのは京都・西本願寺の国宝「御影堂(ごえいどう)」の仕事です。板の上に瓦を葺く工法が取られ、外からは見えませんが、作った板の数は、なんと。
栗山芳博さん:
「28万枚くらいだった。工期が短くて、削るなら寝る時間しかないもので、今なら信じられないわな。段々と遅くまで延ばしていった。(夜)8時になって、8時半、9時、10時、12時。いっぺんに延ばせないので、やっぱり体続かないので(笑)。幸せなことですね、文化財に携われる。先祖さんが長年やってきて、それが続いてきてるから『栗山さんどうですか』って話になってくる」

樹齢250年~300年の木曽の「さわら」
この日、作っていたのは桂離宮にある「月波楼」のこけら板。4万枚から5万枚を作る予定です。
使うのは樹齢250年から300年の木曽のサワラ。軽くて柔らか、さらに水にも強く屋根板にぴったりの材です。それを厚さ3ミリまで「等分」に割っていきます。
栗山芳博さん:
「最初は真ん中いかない。全然、こんな方、行っちゃったり、いろいろした。真ん中を見る、そうすれば真ん中入れば、あとは手が動いていくもんで、反射神経だな」
■4代目も父の背中を追いかけ

4代目の栗山弘忠さん
10年ほど前に会社を受け継いだ4代目の弘忠さん(49)。
弘忠さんも父の背中を追いかけ大学卒業後、家業に入りました。