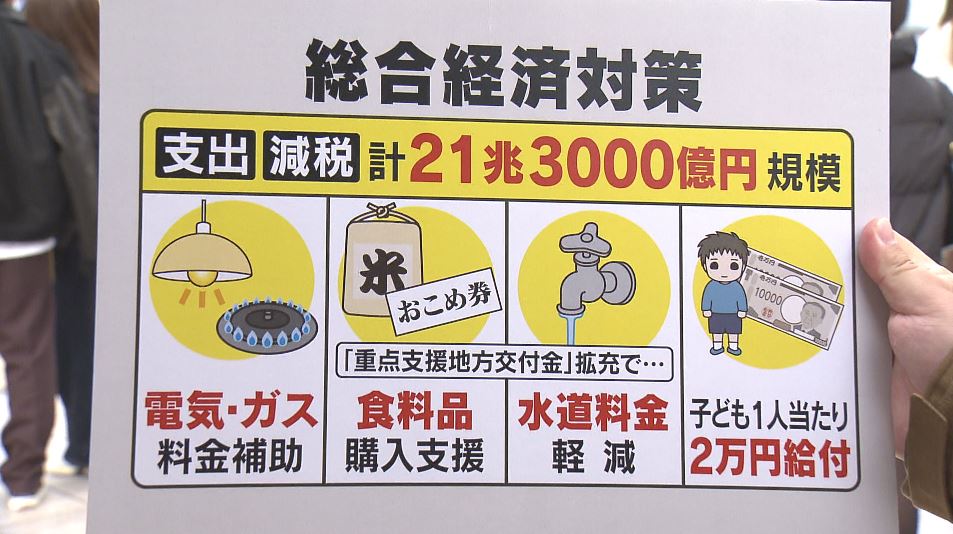
総合経済政策
高市政権は11月21日、電気・ガス料金の補助や子育て応援手当などを盛り込んだ、21兆3000億円規模の経済対策を閣議決定しました。私たちの暮らしにも直結する今回の対策、街の人はどう受け止めているのでしょうか。
11月21日に閣議決定した高市政権として初めてとなる経済対策。ガソリン税の暫定税率の廃止など減税分と合わせて約21兆3000億円規模となります。
生活に直結する家計への支援策としては、電気・ガス料金の補助を2026年1月から3月までの3カ月間で、標準の1世帯当たり合計7000円程度行います。
自治体が自由に使える「重点支援地方交付金」を拡充し、自治体が「おこめ券」などで1人あたり3000円程度の食料品支援を行えるようにします。
このほか、子育て応援手当として子ども1人あたり2万円の給付も盛り込まれました。
街の人はどう受け止めているのでしょうか。
須坂市(30代):
「電気、ガス、水道は絶対にかかるお金なので、ここが減るのはありがたい」
長野市(60代):
「電気もガスも食料品も、みんなうれしいよね、みんな使うんだから。灯油(の補助)もあればいいね」
松本市(50代):
「冬の間は、暖房費がかかるので、電気代は安いとうれしい。エアコン、こたつ、お風呂もそうだし、ありがたい」
値上がりが続く電気・ガス料金の補助には歓迎の声が多く集まりました。
一方、賛否が分かれたのが子育て応援手当です。児童手当の枠組みを活用し、高校生年代までが対象で、所得制限はありません。
松本市(40代):
「率直にありがたい。子どもも2人いるので2万円の給付が増えるのはありがたい。一時的なものでなくて、継続的に給付をやってもらえたら、さらにありがたい」
松本市(40代):
「物価がどんどん上がっているじゃないですか。だから、援助していただけるならいいな。現金給付のほうが、自分の使いたいところに使える」
長野市(70代):
「不公平感があると思うんです。子どもいない人もいるし、いても一番お金かかるのは大学入ってからです。大学の授業料をただにしてほしいです」
安曇野市(50代):
「ちょっと不公平感はありますけど、本当は所得税とか社会保険料とか下げてくれればうれしい」
松本市(50代):
「給付だと一時しのぎなので、そうでない方法がいいかなと。反対ではないけど、あまり効果はないかな」
大型の経済対策は私たちの暮らしにどう影響するのでしょうか。





