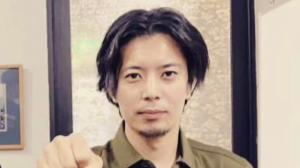■無念の思いを胸に

横浜市の佐藤さん(女性59歳)は、産婦人科医としてクリニックを営んでいた夫を、がんで亡くしました。
「主人が亡くなった直後は、何もできなかった自分の無力感、罪悪感とか申し訳なさとかの気持ちが強くて、悲しくて悲しくてという毎日だった」と振り返ります。
しかし、お形見ベアとの暮らしの中で、徐々に心境が変化します。
「主人はおそらく精一杯生きたし、やりたいことは全部やっていけたんじゃないか、そういう気持ちが強くなってきて、主人の死を受け止めることができました」
夫は「重複がん」で命を落としました。重複がんは、あるがんの治療後に別の部位に新たながんが発生するもので、診療科が異なるために発見が遅れてしまうケースも少なくないとされます。
夫は、医師でありながらそれに気づけなかったことを悔やみ、重複がんの知識があまり知られていない現状から、新聞社などに記事執筆を呼び掛けるなど啓もう活動に力を入れていました。
佐藤さんは、助産師として夫と一緒に働いていたクリニックで今も働いています。
夫が亡くなって1年ほど休養した後、再び仕事に戻るにあたり、夫の想いを受け継いで患者に接していこうと決めました。
「主人は自分と同じ悔しい思いをする人が一人でも減って欲しいと願っていましたので、患者さんの体調の変化とかを早く気づいて差し上げて、検査につなげていただきたいという思いで、日々頑張って診療しています」
■再出発の日々をお形見ベアとともに

「グリーフケア」という言葉が注目されています。家族など大切な人を病気や事故で失った深い悲しみを抱える人への、心の支援を指します。
関西学院大学教授の坂口幸弘さんは「死別という体験は誰もがいずれは経験する。その悲しみやつらさが非常に長引いたり重篤になると、うつ病などの心のリスクもあり、そうならないような支援が必要」と語ります。
お形見ベアについては、「亡くなった方との繋がりは続いていく。残された者の心の拠り所になる点では、お形見ベアもグリーフケアとしての役割を果たしている」と評価します。
高齢化に伴う多死社会化は進み、亡くなる人の数は2040年頃にピークを迎えるとされています。別れと向き合う場面も増えるといえ、それとともにグリーフケアの重要性もより高まっていくのではないでしょうか。
最愛の家族を失う大きな悲しみを背負った人たちは、再出発の日々をお形見ベアとともに過ごし、ベアに、そして周りの人たちに力をもらいながら、確かな希望の毎日を歩み続けています。
〔この記事は、NBS長野放送で2025年9月26日に放送した「NBSフォーカス∞信州 いってくるね。クマちゃんのグリーフケア」をもとに構成しています〕