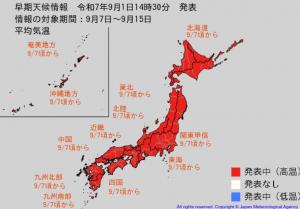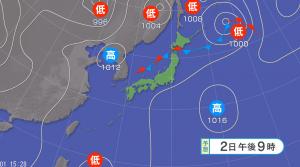地下壕の入口とみられる場所の調査
戦後80年「幻の地下壕」です。終戦間際、長野市周辺の善光寺平で、いわゆる「松代大本営」など「本土決戦」に向けた準備が急ピッチで進んでいました。山一つ隔てた現在の筑北村坂井地区(旧坂井村)でも地下壕の建設が計画されました。「全村動員」が叫ばれながら、わずか2日間で終わった工事について住民たちの貴重な証言が得られました。
■善光寺平で進む「本土決戦」準備

「松代大本営」象山地下壕(長野市松代町)
太平洋戦争末期の1945(昭和20)年、現在の長野市松代町に大本営および政府の中枢などを移転しようと、陸軍が主導して象山・舞鶴山・皆神山の3つの山などに爆撃にも耐えられる地下壕を作る工事が進んでいました。
最も規模の大きい「象山地下壕」は、長野市の篠ノ井旭高校(現:長野俊英高校)郷土研究班の生徒の研究や保存・活用を呼びかける活動が実を結び、長野市が一部を整備して来場者の安全を確保し、1990(平成2)年から一般に公開しています。
また、舞鶴山の地下壕は気象庁の地震観測所に活用され、天皇御座所として作られた建物も現存しています。

「大本営海軍部壕」(長野市安茂里小市)
松代から北西に10キロ余り離れた現在の長野市安茂里小市でも海軍が地下壕の工事に着手し、100メートルほど掘ったところで終戦を迎えました。地元有志で作る「昭和の安茂里を語り継ぐ会」の尽力で、2021(令和3)年から「大本営海軍部壕」として資料館とともに公開しています。(注:事前予約制)

「本土決戦」に向けた善光寺平の施設
現在の長野市大豆島にあった長野飛行場の拡張や、長沼地区の飛行場新設、篠ノ井共和地区の高射砲陣地、そのほか通信施設や地下倉庫などの準備が各地で行われ、「本土決戦」に向けた準備が着々と進んでいたのです。
■山一つ隔てた村にも地下壕計画が...

筑北村坂井の山秋集落
善光寺平から南西へ山一つ隔てた筑北村の坂井地区。当時は坂井村と言った山里にも戦争の影が忍び寄りました。山秋という小さな集落の背後にある山に地下壕を作る計画が持ち上がったのです。

善光寺平の西に丸く突き出た姨捨山(長野市から)
当時、松代大本営の工事に携わっていた将校が、坂井村の地下壕を指すとみられる記述を残しています。
「極秘裏に地下壕の適地を姨捨山の西側高地・松代より西10キロに探して歩いた」(「軍事史学」第二十巻第二号 『松代大本営工事回顧録』より)
「終戦の日は姨捨山の裏側の次の候補地を見に行っていて、正午に天皇の重大放送があると知らせがあって急いで帰ってきました」(「松代地下大本営」 林えいだい より)