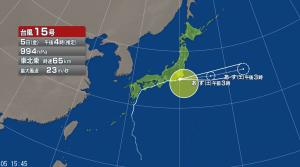■合宿で育む「チームワーク」と「憧れ」
また、長野陸上競技協会の駅伝部長の丸山健志さんは「今の都道府県対抗駅伝に関しましては、直前の1月の合宿は、大学生も実業団も一緒に合宿をする。特に大学生に関しては箱根駅伝を終わって翌日に合宿に合流してもらう。チームワークがつくれるというのが一番大きいと思います。これは他所の県ではまず類がないことだと思います」と話し、胸を張る。
特徴的な強化策として挙げられるのが「合宿」。都道府県対抗駅伝の合宿は、前年の3月にスタートし、ほぼ毎月行われている。中学生から社会人まで参加してもらうことで、チームとしての一体感も育まれると言う。
特に中学生にとって「憧れの先輩」と一緒に走ることは大きな刺激になる。
今年1月、都道府県対抗男子駅伝で中学生区間を走った選手は、「先輩方の練習に向かう姿勢や日常生活などでさまざまなことを教えてもらった。合宿などがあるからいろんなことを教えてもらって、陸上の結果にもつながるし、人間としても大切なことを学べる」と話し、合宿は成長できる環境だという。
中学生の頃から刺激を受け、先輩や指導者に憧れて強豪校へ集まり、切磋琢磨する。
卒業後は合宿などを通じてこれまでの経験を次の世代に伝えていく。この憧れや経験の「循環」が強さの伝統を築いている。
金さんは、「男子は佐久長聖に集まってきて、女子は長野東に集まってきてみたいな。そういう流れはできています。高校駅伝で強いだけじゃなくて、OB・OGが活躍しているじゃないですか。日本代表に何人もなっているし、大学駅伝でも活躍しているし、世界大会でも活躍している。そういう、ロールモデルになるような、ヒーローになるような先輩たちがたくさんいるからだと思う」と分析している。
■「駅伝愛」が支える伝統と強さ
さらに県縦断駅伝や市町村対抗駅伝など歴史ある大会が多いのも長野県の特徴。幅広い年代のランナーが交流することによって、競技力の向上や競技人口の増加も期待できると言う。
大会を通じて県民の関心も高まり、熱い声援に。都道府県対抗男子駅伝でも長野県からの応援団や広島の県人会が駆け付けていた。
信州駅伝サポート会の伊藤利博さんは、「昔から県縦断駅伝とか、信毎マラソン、のちの長野マラソン、長野県には駅伝文化が育まれたと思う。それが今の結果につながっているのでは」と話す。
■「心」を大切にする県民性
強さには、やはりさまざまな理由があるようだが、そもそも駅伝に対する県民の「熱量」の高さはどこから来ているのだろうか。
丸山健志駅伝部長は、「駅伝は特に『心』を大事にする競技ですので、思いやりであったり、そういうのが長野県民は非常に好むんじゃないかなと思います」と話す。
たすきをつないで心一つにゴールに向かう。
環境や伝統だけでなく、県民の「駅伝愛」が王国を支えているとも言えそうだ。