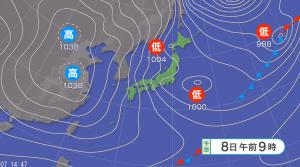長野県松本地域で昔から食べられている「からしいなり」です。その名の通り、からしの効いたいなり寿司です。なぜ、松本の味として定着したのか、「深掘り」してみました。
甘く煮た油揚げに、酢飯を詰めた「いなり寿司」。稲荷神社の神の使い「狐」に、好物の油揚げをお供えしてきたことが名前の由来とされ、江戸時代から食べられていたと言われています。
一方、松本でよく食べられている「いなり寿司」は、油揚げが裏返しになっています。
しかも…
(記者リポート)
「あまじょっぱい味の後にピリッとくる辛さがクセになりますね。辛すぎる感じも全くなく、とてもおいしいです」
内側にはしっかりと「からし」が塗られています。
記者:
「これ何かご存じ?」
松本市民:
「からしいなり」
「からしいなりと違う?からし好きだから、両方あればこっち買います」
長野市民:
「見たことはあります。(どんないなり寿司か知ってる?)ひっくり返して包んだだけってイメージですけど」
松本地方伝統の味「からしいなり」。市内では普通の「いなり寿司」と区別している人が多く、油揚げが裏返っていれば「からしいなり」と認識されているようです。「からしいなり」はスーパーでも…。
購入客:
「好きですよ。甘いだけじゃないっていうか」
「孫が好きで、私が出かけたときに帰りにこれを買って帰って、これからお茶を飲もうかと思って(笑)」
「ツルヤ」は県内全店に「からしいなり」を置いていますが、松本地域は、他地域よりも売り上げが多いそうです。
ツルヤ なぎさ店・山岸秀武次長:
「特に松本市内のお店は需要が高いと思います。平日で30パック前後、販売してますね。週末で40から50パックくらい。6時半くらいには完売していますね」
仕出し弁当店の「若増伊平寿司本舗」。およそ60年前の創業時から「からしいなり」を販売しています。しょう油と砂糖で甘辛く煮た油揚げを裏返して…内側にからしを塗り、酢飯を詰めます。
普通のいなり寿司も販売していて人気は「ほぼ互角」。からしいなりは多い時で1日200個近く売れるそうです。
塩尻市出身:
「大好きです。子どもの頃からよく母が作っていたので」
長野市出身:
「からしが効いているというか、鼻に抜ける感じがいいなと。出身は長野市なんですよ。(子どもの頃、食べたことは?)ないんですよ、こっち来てからですね」
若増伊平寿司本舗・上島英雄さん:
「(子どもの頃から知っていた?)いやー全然知らなかったです」
創業者の上島英雄さんは伊那市出身。「からしいなり」は知りませんでしたが、松本で店を開く際、メニューに加えました。
若増伊平寿司本舗・上島英雄さん:
「自分が仕事始めた頃、(からしいなりの)うわさを聞いていたんだけど(普通の)おいなりさんだけじゃ単純だなって感じもあったし、ピリッとする方がうまいかなと」
起源はわからないということですが、上島さんは油揚げを「裏返す」理由は察しがつくと言います。
若増伊平寿司本舗・上島英雄さん:
「おいなりさん(油揚げ)の中身ってゴツゴツしてるじゃない。返すことによって、からしも塗りやすいということもあるし、(普通のいなり寿司と)見分けやすいということもあると思いますね」
母親が作っていたと話してくれた、こちらの女性も…
塩尻市出身:
「(揚げ、裏返しにしていた?)してました。なので子どもの頃、裏返しと表で見分けて、いただいてました」
では、「からしいなり」はどうやって生まれ、なぜ、松本に定着したでしょうか。地域の歴史・文化に詳しい松本市立博物館の木下守館長に聞きました。
松本市立博物館・木下守館長:
「おそらく『揚げにからし』という組み合わせが先にあって、おいなりさんにも、からしの揚げを使ったらおいしいんじゃないかという順番なのかなと想像はしますけど、確証はないですね」
「からしいなり」には神社に関係した「ルーツ」とみられる食べものがあります。毎年1月14日、無病息災を願って行われる筑摩神社の「篝火神事(かがりびしんじ)」。
筑摩神社・林邦匡宮司:
「この篝火にあたり、からしあげを食べれば、1年間無病息災で過ごせるんだという言い伝えで行われています」
参拝者がこぞって買っているのは、神事に合わせて売られる「筑摩からしあげ」。甘辛く煮た油揚げと、からしがセットになっています。油揚げについては、年明けに厄除けや無病息災を願って「大豆」を食べる風習があったことと関係があるのではと木下館長はみています。
松本市立博物館・木下守館長:
「正月、あるいは2月くらいにかけての行事に大豆、あるいは大豆を原材料とした食品が行事に用いられる。節分の豆まきが一番わかりやすいと思うんですけど。収穫して調整の済んだ大豆製品を、儀礼でいただくというのが根底にあるのかなと」
松本では、葬儀や法要の際、精進料理として油揚げを甘辛く煮たものが出されることがあり、それに倣ったものという見方もできるそうです。からしをつける理由ははっきりしませんが、相性は抜群です。
松本市立博物館・木下守館長:
「甘辛く煮た揚げには、からしが合うかなと思うので、そんなことでこの地域では親しまれているのかなと思いますけど」
「製造元」にも聞いてみました。
「からしあげ」の油揚げは、市内に工場を持つ「田内屋」が作っていて「筑摩揚げ」という名で販売しています。神社に油揚げを納めるようになったのは、筑摩に工場を建てた「昭和43年ごろ」ということはわかっています。
田内屋・井上雄太専務:
「筑摩神社さんはそれよりもさらに前から、お祭りのときは、参拝者の方に(からしあげを)出されているというのは聞いています」
「からしあげ」の歴史は古いようで、こちらでも起源ははっきりしませんでした。
ただ、煮た油揚げとからしは相性が良く、「からしいなり」は「からしあげ」の応用ではないかと考えられるそうです。
田内屋・井上雄太専務:
「からしいなりっていうのは、どちらかというとご商売されている方がアイデアで作ったものなので、どこかでもしかしたら、筑摩神社のからしあげを見た方がいらしたのかもしれないですけど」
2月5日は旧暦の「初午」。稲荷神社の祭りの日で、いなり寿司を食べると縁起が良いとされています。
甘く煮た油揚げに、酢飯を詰めた「いなり寿司」。稲荷神社の神の使い「狐」に、好物の油揚げをお供えしてきたことが名前の由来とされ、江戸時代から食べられていたと言われています。
一方、松本でよく食べられている「いなり寿司」は、油揚げが裏返しになっています。
しかも…
(記者リポート)
「あまじょっぱい味の後にピリッとくる辛さがクセになりますね。辛すぎる感じも全くなく、とてもおいしいです」
内側にはしっかりと「からし」が塗られています。
記者:
「これ何かご存じ?」
松本市民:
「からしいなり」
「からしいなりと違う?からし好きだから、両方あればこっち買います」
長野市民:
「見たことはあります。(どんないなり寿司か知ってる?)ひっくり返して包んだだけってイメージですけど」
松本地方伝統の味「からしいなり」。市内では普通の「いなり寿司」と区別している人が多く、油揚げが裏返っていれば「からしいなり」と認識されているようです。「からしいなり」はスーパーでも…。
購入客:
「好きですよ。甘いだけじゃないっていうか」
「孫が好きで、私が出かけたときに帰りにこれを買って帰って、これからお茶を飲もうかと思って(笑)」
「ツルヤ」は県内全店に「からしいなり」を置いていますが、松本地域は、他地域よりも売り上げが多いそうです。
ツルヤ なぎさ店・山岸秀武次長:
「特に松本市内のお店は需要が高いと思います。平日で30パック前後、販売してますね。週末で40から50パックくらい。6時半くらいには完売していますね」
仕出し弁当店の「若増伊平寿司本舗」。およそ60年前の創業時から「からしいなり」を販売しています。しょう油と砂糖で甘辛く煮た油揚げを裏返して…内側にからしを塗り、酢飯を詰めます。
普通のいなり寿司も販売していて人気は「ほぼ互角」。からしいなりは多い時で1日200個近く売れるそうです。
塩尻市出身:
「大好きです。子どもの頃からよく母が作っていたので」
長野市出身:
「からしが効いているというか、鼻に抜ける感じがいいなと。出身は長野市なんですよ。(子どもの頃、食べたことは?)ないんですよ、こっち来てからですね」
若増伊平寿司本舗・上島英雄さん:
「(子どもの頃から知っていた?)いやー全然知らなかったです」
創業者の上島英雄さんは伊那市出身。「からしいなり」は知りませんでしたが、松本で店を開く際、メニューに加えました。
若増伊平寿司本舗・上島英雄さん:
「自分が仕事始めた頃、(からしいなりの)うわさを聞いていたんだけど(普通の)おいなりさんだけじゃ単純だなって感じもあったし、ピリッとする方がうまいかなと」
起源はわからないということですが、上島さんは油揚げを「裏返す」理由は察しがつくと言います。
若増伊平寿司本舗・上島英雄さん:
「おいなりさん(油揚げ)の中身ってゴツゴツしてるじゃない。返すことによって、からしも塗りやすいということもあるし、(普通のいなり寿司と)見分けやすいということもあると思いますね」
母親が作っていたと話してくれた、こちらの女性も…
塩尻市出身:
「(揚げ、裏返しにしていた?)してました。なので子どもの頃、裏返しと表で見分けて、いただいてました」
では、「からしいなり」はどうやって生まれ、なぜ、松本に定着したでしょうか。地域の歴史・文化に詳しい松本市立博物館の木下守館長に聞きました。
松本市立博物館・木下守館長:
「おそらく『揚げにからし』という組み合わせが先にあって、おいなりさんにも、からしの揚げを使ったらおいしいんじゃないかという順番なのかなと想像はしますけど、確証はないですね」
「からしいなり」には神社に関係した「ルーツ」とみられる食べものがあります。毎年1月14日、無病息災を願って行われる筑摩神社の「篝火神事(かがりびしんじ)」。
筑摩神社・林邦匡宮司:
「この篝火にあたり、からしあげを食べれば、1年間無病息災で過ごせるんだという言い伝えで行われています」
参拝者がこぞって買っているのは、神事に合わせて売られる「筑摩からしあげ」。甘辛く煮た油揚げと、からしがセットになっています。油揚げについては、年明けに厄除けや無病息災を願って「大豆」を食べる風習があったことと関係があるのではと木下館長はみています。
松本市立博物館・木下守館長:
「正月、あるいは2月くらいにかけての行事に大豆、あるいは大豆を原材料とした食品が行事に用いられる。節分の豆まきが一番わかりやすいと思うんですけど。収穫して調整の済んだ大豆製品を、儀礼でいただくというのが根底にあるのかなと」
松本では、葬儀や法要の際、精進料理として油揚げを甘辛く煮たものが出されることがあり、それに倣ったものという見方もできるそうです。からしをつける理由ははっきりしませんが、相性は抜群です。
松本市立博物館・木下守館長:
「甘辛く煮た揚げには、からしが合うかなと思うので、そんなことでこの地域では親しまれているのかなと思いますけど」
「製造元」にも聞いてみました。
「からしあげ」の油揚げは、市内に工場を持つ「田内屋」が作っていて「筑摩揚げ」という名で販売しています。神社に油揚げを納めるようになったのは、筑摩に工場を建てた「昭和43年ごろ」ということはわかっています。
田内屋・井上雄太専務:
「筑摩神社さんはそれよりもさらに前から、お祭りのときは、参拝者の方に(からしあげを)出されているというのは聞いています」
「からしあげ」の歴史は古いようで、こちらでも起源ははっきりしませんでした。
ただ、煮た油揚げとからしは相性が良く、「からしいなり」は「からしあげ」の応用ではないかと考えられるそうです。
田内屋・井上雄太専務:
「からしいなりっていうのは、どちらかというとご商売されている方がアイデアで作ったものなので、どこかでもしかしたら、筑摩神社のからしあげを見た方がいらしたのかもしれないですけど」
2月5日は旧暦の「初午」。稲荷神社の祭りの日で、いなり寿司を食べると縁起が良いとされています。